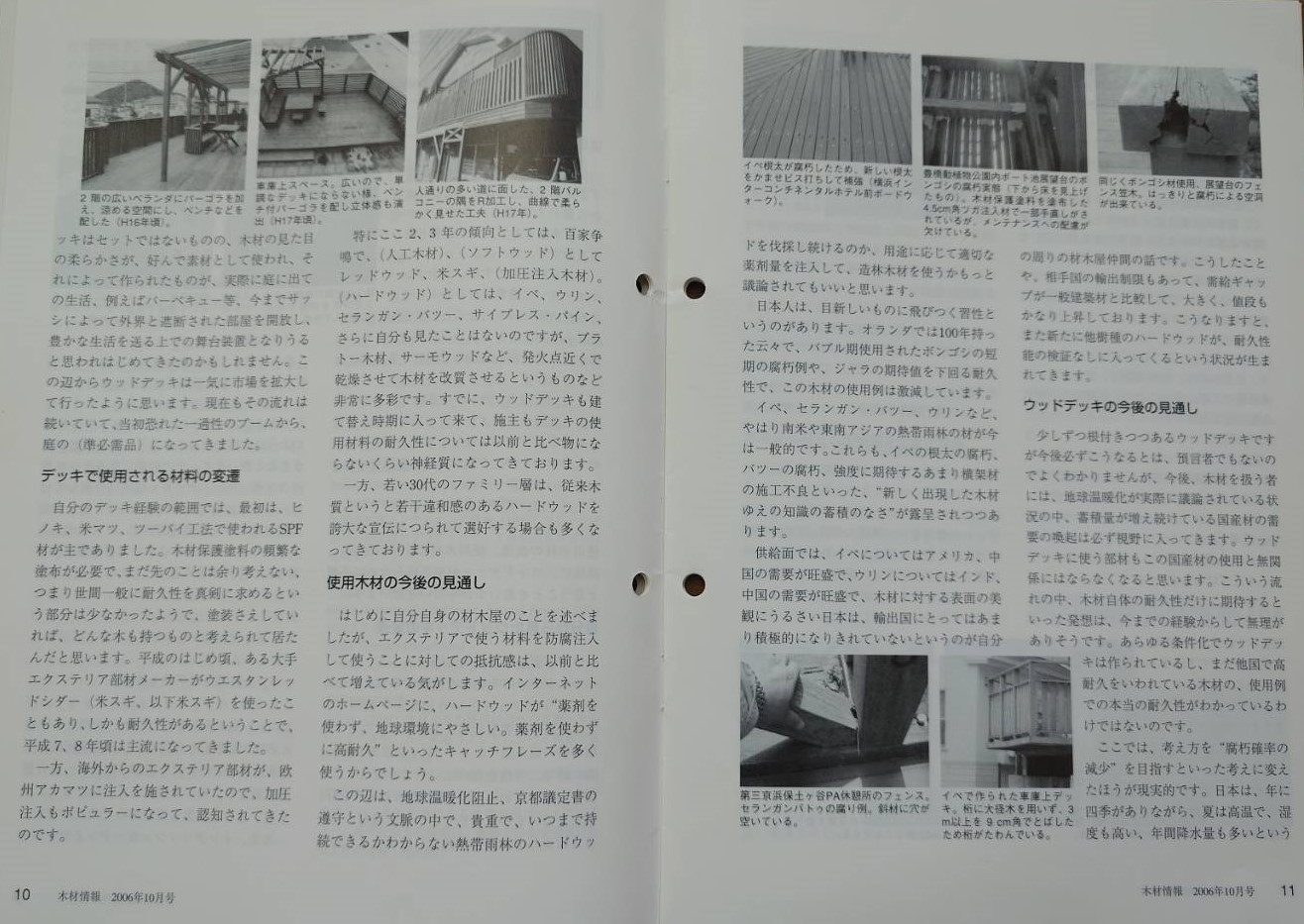
平成の初期、あるいはその前には、外構用として使用される多かったのが米松(ダグラスファー)でした。松というから、油分が多く腐りにくいと思われたわけですが、ウッドデッキにすると屋根のない露天で日々、自然界にあるわけで、そういう場所での耐久性は低かったのです。
そのような理解が進んだ頃に、ソフトウッド(針葉樹)として、耐久性が高いということでレッドウッド(セコイア系の樹種)・レッドシダーが使われ出しました。
また、ハードウッドも1990年代には、南米(イペ等)・東南アジア(セランガンバツ・ウリン等)・オーストラリア(ジャラ)・アフリカ(ボンゴシ)などが入ってきました。
最初のころは、耐久性の客観的評価(具体的にはハザードレベル)は、日本では確立されていなかったと思います。
また、海外での樹種の客観的評価も気候も違うし、腐朽・加害させる生物の違いがあり信用できるわけではないことも分かってきたのです。
日本では、遅れて客観的評価値(K1~K5)が作られそれによって、急速に正確な判断もしやすくなりました。
耐久性の評価の実験も、評価の方法も具体化してきたのです。
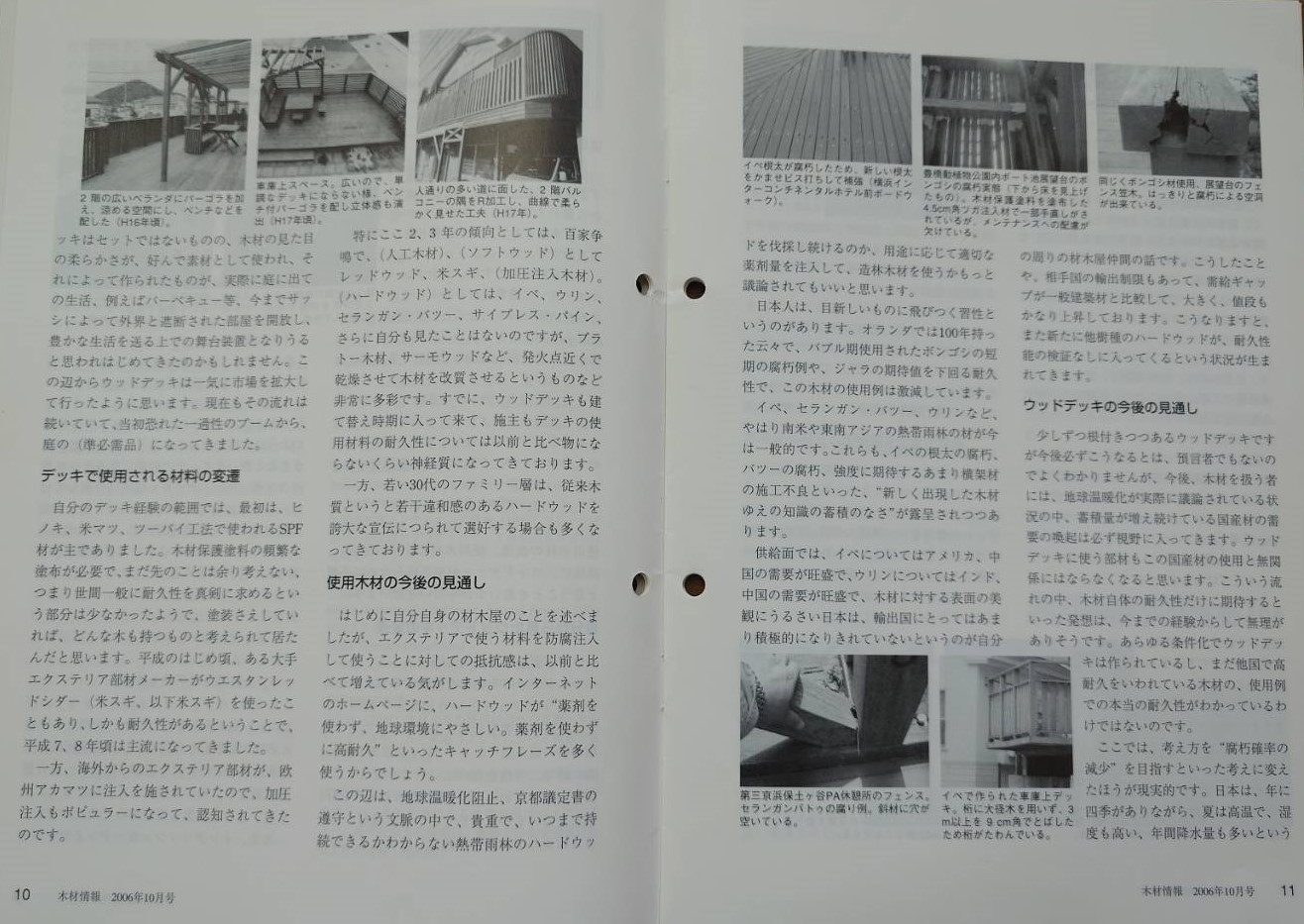


コメント